平和への想い-IIWCと伊藤延男先生
平和への想い-IIWCと伊藤延男先生
Thoughts on Peace - IIWC (ICOMOS International Wood Committee) and Dr Nobuo Ito
土本 俊和 Toshikazu TSUCHIMOTO
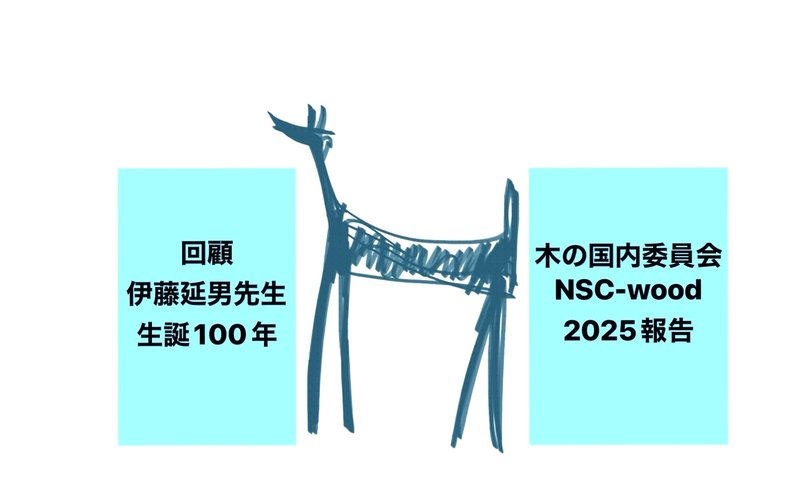
今年10月に開催されるネパールでのイコモス総会では、木の委員会IIWC(ICOMOS International Wood Committee)が設立50周年ということで、IIWC 50 yearsというポスターセッションが持たれ、日本から出す予定で作業を進めている。IIWCの設立は、伊藤延男先生がまとめられた資料によると、1975年で、そのときから50年経ったという理解になる。
1975年は伊藤先生が50歳のころと思う。そのとき中学生だった私はアントニオ猪木とモハメド・アリの対決をテレビで見るなどしていて、この年が重要伝統的建造物群保存地区制度が動き始めた年であったと知るに至ったのは数十年後のことである。
イコモスの設立が1965年で、前年の1964年に採択されたヴェニス憲章は、「歴史的記念物は単体としてだけでなく、群としても考えられなければならないこと」を謳っている。伊藤先生は重伝建制度についてときどき話してくれた。たとえば、建築基準法の施行令を重伝建制度につけなかったのはミスだったかもしれない、とかである。重伝建制度の創始者を自認されたこの回顧は、その背景にイコモスがあるだろう。イコモスの出発点であるヴェニス憲章のうち「群としても考えられなければならないこと」が1975年に日本で具現化されたのが重伝建制度であった。重伝建制度は、どこから来て、どのように日本で形になり、今に至っているのか、という時の流れを川の流れを眺めるかのように、うかがっていた。
IIWC設立から19年後の1994年は奈良ドキュメントが採択された年で、今から見ると31年前になる。この年はIIWCが大きな役割を果たした年であったと理解したい。というのも、この1994年がラルセン氏(Knut Einar Larsen)による『Architectural Preservation in Japan』がIIWCからパブリッシュされた年だからである。ラルセン氏によるこの一冊が奈良ドキュメントに与えた影響、とくに国外の専門家に与えた影響は、無視できないはずである。ラルセン氏は、これを書くに先立って、神宮司庁山田工作場など、日本のしかるべき場所をまわった。ラルセン氏を案内されたのが伊藤先生であった。「ラルセンが書いたのは全部僕が教えたことだよ」とさえ言われたことがあった。
2012年のメキシコ・グアダラハラでのIIWCの年次会議で、伊藤先生は、ラルセン氏と彼の息子さんとの交流を、研究発表会の場で発表された。この会議で、"木の遺産の保存に関する原則"の改訂を実質的に進めていくことが合意された。翌年2013年、伊藤先生は姫路でのIIWCの会議に尽力された。継続審議で終わったこの会議の後、IIWC委員長であったタンポーネ氏(Gennaro Tampone)を、法隆寺や東本願寺など、全解体修理を含む現場に案内されるなど、タンポーネ氏の理解を促す努力をなされた。この努力は、ヨーロッパの専門家に全解体修理ほか、諸々の日本の木造建築に関する事柄が誤解なく理解されることを願う努力であったと思う。
誤解なく理解されることを願う以上に、誤解なく理解されることに至ることを、伊藤先生は信念として持っておられたと思う。イタリアで開催された会議のときだったか、第二次世界大戦でのポー川について話された。ポー川北部で戦災にあった遺産へ、戦後すぐ、国を超えて、現場に向かった人たちがいたという。そのときに、ヨキレット氏(Jukka Jokilehto)の先生とタンポーネ氏の先生が現地で出会った、とのことであった。
みんな、いっしょなんだよ、と言われた。伊藤先生は、1925年3月お生まれなので、1945年8月15日を20歳で迎えたことになる。イコモスの会議は、物見遊山みたいなところが多いけど、と言われながら、髪の色が様々な人々と巡る見学会を先生は大事にされていた。大切なのは平和なんだよ、と言われたのはポー川について話されたときであった。
木の遺産の保存に関する原則は、いくつかの会議を経て、2017年のニューデリーでの総会で採択された。伊藤先生が亡くなられたのは2015年であった。