アンドレア・パーネ氏の来日と「ヴェニス憲章60周年 ―人類の遺産保存のために」イベント開催について
アンドレア・パーネ氏の来日と「ヴェニス憲章60周年 ―人類の遺産保存のために」イベント開催について
Prof. Andrea Pane’s (University of Naples Federico II) visit to Japan and the “60 years of the Venice Charter: an international tool for the conservation of the heritage of humankind” event
ウーゴ ミズコ Mizuko UGO
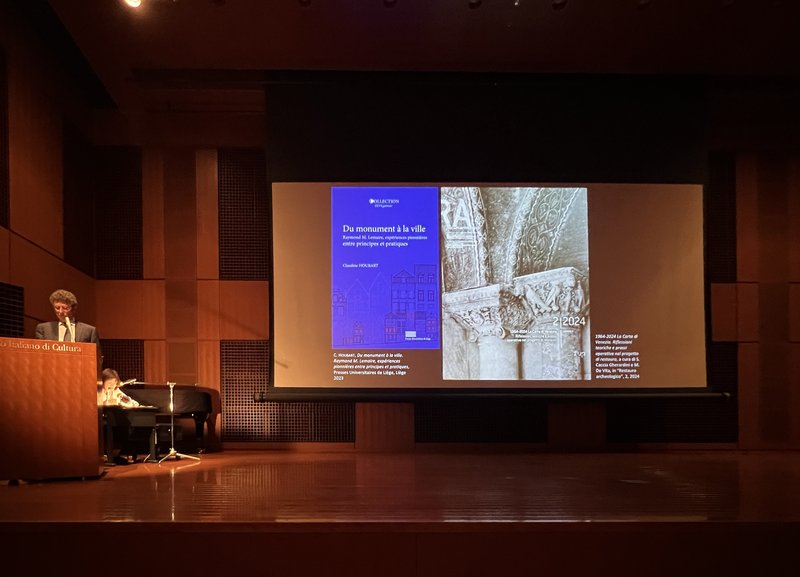
去る6月3日に、大阪・関西万博見学を目的に、フェデリコ2世ナポリ国立大学教授アンドレーア・パーネ(Andrea Pane)氏が来日した。保存建築家にして建築史家であるA.パーネ氏は、長年ヴェニス憲章に関する研究を続けており、その研究成果を披露頂くとともに、日本建築の保存修理の面白さを堪能して頂く機会を設けることになった。
文化財建造物保存技術協会の常務理事(当時)の野尻孝明氏のご厚意で、A.パーネ氏は岐阜県可児郡御嵩町・願興寺本堂の保存修理現場を訪れる機会を得た。現場は組み立てが進んでおり、構造補強もほぼ完成しており、日本建築の保存修理の特徴を理解するためのまたとない機会となった。A.パーネ氏によれば、日本建築の保存修理について書籍や会議報告書を読んでも理解できなかった部分が多かったが、実際に現場を訪れて感銘を受けたとのことだった。今後、イタリア等で日本建築の保存修理に関するさまざまな発信が期待される。

現場見学に加え、ヴェニス憲章採択60周年記念として、6月6日に東京のイタリア文化会館において「ヴェニス憲章60周年―人類の遺産保存のために」と題したイベントが、イタリア文化会館と日本イコモスの共催で開催された。A.パーネ氏をお招きし、憲章の意義と作成時の状況についてあらためて考える機会となった。
イベントは、第一部のヴェニス憲章の作成過程に関するドキュメンタリー上映と、第二部の講演会の二部構成だった。第一部のドキュメンタリーは、2024年にイタリア放送協会(RAI)が手掛け、A.パーネ氏が学術監修を務めたものである。今回のドキュメンタリーは、イタリア放送協会が文化省と協力し制作している、国内の文化財とその保存活用を深めるドキュメンタリーシリーズ『イタリア:美への旅』の一エピソード(2024年11月放送)だ。そのタイトルは、ヴェニス憲章の公式出版の副題から「ヴェネツィア1964-人類のための記念建造物」となっており、1964年11月にイタリアの歴史的都市ヴェネツィアで開催された国際会議に焦点を当てているものの、その成果は地域や国を超え、世界のどの国民のためにもなる文化財の扱い方を目指していたことが伝わる。ヴェニス憲章作成の時代背景と国際会議の参考資料や古写真、さらに関係者や現役の建築家と文化財担当官へのインタビューを通じて、当初の試みと現在における憲章の意義をハイライトするドキュメンタリーとなった。それは、文化財と歴史都市を題材にした美しい映像に加え、テンポの早い映像展開で、冒険のような脚本で興味を喚起するような構成となっている。飽きさせないストーリーによって、ヴェニス憲章に関わったイタリア国内外の専門家の志が描かれており、過去のみならず文化財の整備運営の現在についても言及している。最終的には、ヴェニス憲章が引き金となって、現在もさらに発展している文化財の保護活動と、それを対象とした国際協力の今後についても期待をもたせる。
イベントの第二部は、ドキュメンタリーの内容と関連した、A.パーネ氏の講演「ヴェニス憲章60周年-その歴史的背景と成立過程」であった。世界的に利用されるヴェニス憲章だが、その作成過程や内容の解釈、さらに複数の訳の関係性については現在も研究が続いている。ヴェニス憲章の作成に深く関わったフェデリコ2世ナポリ国立大学教授ロベルト・パーネ(Roberto Pane, 1897-1987)の孫であるA.パーネ氏は、祖父の資料等を使用し、ヴェニス憲章の成立過程とその歴史的背景について長年研究を進めてきた。そのため、ドキュメンタリー作成のためにテレビ局よりアドバイザーの立場として招かれたものの、途中から主役を務めることになったという。
今回の講演では、のちにヴェニス憲章の大きな成果として認められている、歴史的建造物の保存修理が単体の建物のみならず周辺の歴史的都市や景観も含むこと、さらに、保存修理作業における残存部分と新築との関係性についてより掘り下げることを目的に、以下の内容が取り上げられた。1964年に歴史的建造物を対象とした国際会議がヴェニスで開催される運びとなったイタリア側の国際機関への働きかけや時代背景、さらに、ヴェニス憲章の作成に関わった様々な国の専門家の関わりについてである。そのなかで、イタリア人とフランス語圏の専門家の憲章作成への具体的な貢献に関する言及がなされた。
1931年の「アテネ憲章」には既にイタリア人の建築家が関わっていたものの、歴史都市空間がまだそれほど注目されていなかった。しかしその後、イタリア国内では都市計画と歴史的建造物の保存修理の関係性に関する議論が活発に行われ、モダニズムを代表する建築家として知られるジュセッペ・パガーノ(Giuseppe Pagano, 1896-1945)等もその議論に積極的に参加するほどだった。そして、第二次世界大戦が勃発し、続く戦災復興により新と旧の関係性の解決がさらに急務となった。そこには、断片的となった歴史都市空間における土地投機との闘いがあらためて都市計画と歴史的建造物とその環境の扱い方に関する議論を加速させ、最も権威のある建築雑誌や新聞や書籍をとおして設計者や都市計画家、そして保存修理建築家等が議論した。1949年に、「都市修復」(restauro urbano)という新しい言葉が生まれるほどだった。1950年代へと継承される都市計画と歴史的環境との関係に関するこの議論は、ヴェニス憲章作成に影響する重要な歴史的背景として紹介された。
ヴェニス憲章を生み出すことになる第2回歴史記念建造物関係建築家技術者国際会議の具体的な企画と調整、さらに会議の次第を作成した中心的な人物が、イタリア北部西ヴェネト州の文化財監督局長を務めたピエロ・ガッツォーラ(Piero Gazzola, 1908-1978)だったことは知られている。しかし、A.パーネ氏は、会議の実施のキーパーソンだったガッゾーラがR.パーネとともにヴェニス憲章の草案を会議の前から幾度も議論したこと、それが会議では議論の基礎となったこと、国際的な文章にするためには、とくにフランス語への翻訳については、フランス語圏の専門家、ベルギー人の美術史家ポール・フィリッポ(Paul Philippot,1926-2016)、フランス人の記念建造物主任建築家ジャン・ソニエ(Jean Sonnier, 1913-2004)、そして特に会議の書記をつとめたベルギー人の建築史家レモン・ルメール(Raymond Lemaire, 1921-1997)の共同作業があったことについて詳細な報告をしてくれた。
このように、ヴェニス憲章は、まず保存修理において歴史的建造物の建築様式の統一を目指す復原行為を避けることを念頭に、文化財が人類共有の財産であること、さらにその対象が単独の建築物のみならず、歴史的環境に及ぶことを示す試みであったことがあらためて了解される。そして、対象が点から面へと広げられるべきことについて、当時は新築と保存修理の境目が現在よりも明確でなく、むしろ現代的な設計を取り入れることをガッゾーラやR.パーネは現在より積極的に考えていたことも再確認できた。
ヴェニス憲章が採択されてから時間がたっているが、関連資料の研究をさらに進める必要性があるだろう。また、ヴェニス憲章の前文に謳われているように憲章の内容は「各国は、それを自国の文化や伝統の枠組みの中で【…】適用することが不可欠である」という指針に沿って、各文化圏において文化財の利活用と人々にとって豊かな環境づくりのために既存の歴史的建造物や歴史的環境の扱い方に関する議論がますます継続発展していくことが重要である。ヴェニス憲章がわれわれに託した多くの可能性について考えさせてくれる講演だった。

(学習院女子大学)